◆正社員中心主義だった
コロナ禍の中での今年の税制改正により、従来の、大企業を対象とする昇給・設備投資促進税制、中小企業を対象とする所得拡大促進税制は、入退職者は少ない方がよいとする雇用維持とベースアップを奨励する正社員中心主義的な制度から新規雇用促進を奨励する税制に、様変わりしました。
◆中小企業を対象とする所得拡大促進税制は
中小企業向けの所得拡大促進税制では、既存の継続雇用者の給与の上昇という適用要件を放棄し、新規・既存を問わず、雇用者全体の給与等支給額を増やせとの制度になり、その増加率が1.5%以上の場合には雇用者給与等支給増加額の15%(2.5%以上増加で教育訓練費の対前年比も10%以上増加なら25%)の税額控除が出来るとの制度になりました。既存従業員の雇用維持よりも、雇用全体を増やして、失業救済への社会貢献してくれることを奨励しているわけです。雇用保険への加入も条件にしていません。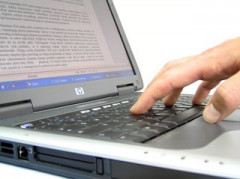
◆新規雇用促進税制へ
中小企業限定ではない、大企業・中堅企業向けの昇給・設備投資促進税制では、設備投資要件が廃止された上、新規雇用をどの程度増やしているかが適用要件になりました。
国内事業所で新たに雇用した雇用保険被保険者に該当する者に1年以内に支給する給与の額の対前年比の増加率2%以上の場合には、新規雇用者給与等支給額の15%(教育訓練費の対前年比が20%以上増なら20%)の税額控除が出来るとの制度になりました。
ただし、解雇の多い事業者を排除するために、前期比雇用者給与増加額が新規雇用者給与総額より少ないような場合には、前期比雇用者給与増加額が控除率を乗ずる対象額の限度となります。
◆雇用調整助成金の扱い
雇用調整助成金等及びこれに類するものの額については、適用判定の場面での増加割合の計算における雇用者給与等支給増加額や新規雇用者給与等支給額の算定ではこれを考慮する必要はありませんが、税額控除額を計算する際の控除率を乗ずる場面では、これをそれぞれから控除する必要があります。
インフォメーション
- 2025-08(1)
- 2024-12(3)
- 2024-11(4)
- 2024-10(5)
- 2024-09(4)
- 2024-08(4)
- 2024-07(4)
- 2024-06(3)
- 2024-05(7)
- 2024-04(2)
- 2024-03(1)
- 2024-02(2)
- 2024-01(2)
- 2023-11(3)
- 2023-10(2)
- 2023-09(3)
- 2023-08(4)
- 2023-07(3)
- 2023-06(2)
- 2023-05(4)
- 2023-04(4)
- 2023-03(2)
- 2023-02(3)
- 2023-01(6)
- 2022-12(2)
- 2022-11(3)
- 2022-10(1)
- 2022-09(2)
- 2022-08(2)
- 2022-07(4)
- 2022-06(1)
- 2022-05(3)
- 2022-04(3)
- 2022-03(1)
- 2022-02(5)
- 2021-12(1)
- 2021-11(5)
- 2021-10(3)
- 2021-09(3)
- 2021-08(3)
- 2021-07(5)
- 2021-06(4)
- 2021-04(4)
- 2021-03(5)
- 2021-02(3)
- 2021-01(2)
- 2020-12(3)
- 2020-11(1)
- 2020-10(4)
- 2020-09(5)
- 2020-08(3)
- 2020-07(3)
- 2020-06(3)
- 2020-05(2)
- 2020-04(6)
- 2020-03(3)
- 2020-01(3)
- 2019-12(3)
- 2019-11(4)
- 2019-10(2)
- 2019-09(4)
- 2019-08(2)
- 2019-07(5)
- 2019-05(3)
- 2019-04(3)
- 2019-03(3)
- 2019-02(1)
- 2019-01(5)
- 2018-12(4)
- 2018-11(2)
- 2018-02(1)
- 2018-01(2)
- 2017-12(1)
- 2017-11(2)
- 2017-10(1)
- 2017-09(1)
- 2017-08(4)
- 2017-07(2)
- 2017-06(2)
- 2017-05(1)
- 2017-04(3)
- 2016-12(2)
- 2016-11(6)
- 2016-10(1)
- 2016-09(2)
- 2016-08(4)
- 2016-07(1)
国税庁が2019年度分の会社標本調査の結果を公表しました。黒字企業の割合は38.4%で10年連続の増加となっています。しかし一方で、黒字企業の所得金額は63兆2588億円で前年度から9.3%も落ち込み、10年ぶりに減少しました。19年度末から新型コロナウイルスの流行が始まったことが影響しているとみられ、コロナ禍の本格的な影響が反映される来年度調査での深刻な落ち込みは避けられそうもありません。
国税庁は毎年、国内の企業の状況を資本金階級別や業種別に調査しています。資本金階級や業種ごとの企業の実態を明らかにすることで、租税収入の見積もりや税制改正などの基礎資料とするためです。最新の19年度版は、19年4月1日~20年3月31日に終了した法人の事業年度が対象となっています。
調査結果によれば19年度の日本の法人数は275万8420社で、前年度から1万9871社増加しました。法人数は7年連続で増加しています。
全体の法人数から連結子法人の数(1万2983社)を差し引いた274万5437社のうち、利益計上法人は105万4080社で、欠損法人が169万1357社でした。利益より欠損のほうが多い「赤字企業」の割合は61.6%で、前年度から0.5ポイント減っています。
<情報提供:エヌピー通信社>
◆制度概要
結婚子育て資金の一括贈与制度は、直系尊属である父母、祖父母から子・孫に結婚・出産・育児の費用を非課税で贈与できる租税特別措置法の制度です。20歳以上50歳未満の受贈者を対象に最大で1000万円(結婚費用は最大300万円)までの贈与が非課税になります。非課税の対象となる費目については、内閣府HPに掲載されています。
平成31年改正で受贈者は、前年分の合計所得金額が1000万円以下に制限されました。令和3年度は次の改正があり、令和5年3月31日まで2年間、延長されました。
◆贈与者死亡時、孫への贈与は2割加算に
贈与者が死亡した日までの贈与額(非課税拠出額)のうち、結婚・出産・育児に使用した金額(結婚・子育て資金支出額)を控除した未使用分(管理残額)は相続税の課税対象となっていましたが、新たに令和3年4月1日以降の孫への贈与は、配偶者および一親等の血族以外(代襲相続人である孫・孫養子を除く)への贈与に適用される、相続税額の2割加算の対象となりました。世代間の資産移転を促進する非課税贈与として創設された制度は、相続税法の取扱いがさらに適用され、利用しにくくなりました。
◆認可外保育施設も非課税の対象になります
非課税の対象となる育児費用の範囲に、新たに1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事などから認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付された施設に対する保育料の贈与も対象となりました。証明書を交付された施設のリストをHPで公開している自治体もあります。
◆非課税申告書は電子提出も可
この制度の適用を受けるため、取扱金融機関を経由して提出する非課税申告書は、令和3年4月1日より、電磁的方法によっても提出できるようになっています。
◆生活資金の贈与はそもそも非課税です
ところで結婚・子育て資金一括贈与の制度を利用しなくても、相続税法では、もともと夫婦、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者からの生活費や教育費に充てるための贈与は非課税とされています。結婚・出産・育児の費用を都度、贈与する、贈与額はすべて使いきる、結婚式披露宴の費用は、双方で費用を分担する、贈与者の送金履歴、受贈者の支払記録を残すなど備えをしておきましょう。
◆3年に一度の評価替え
令和3年度は、3年に一度の固定資産の評価替えの年(基準年度)です。新しい評価額は、令和4年度、令和5年度まで3年間適用され、市区町村の固定資産税納税通知書および課税明細書に記載されています。
◆令和3年度は負担調整措置で前年並み課税
土地の評価には、負担調整措置があります。固定資産の評価額に対する税負担に地域や土地による格差があるのは税の公平の観点から問題があることから、負担調整措置により負担水準(評価額に対する前年度課税標準額等の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地については段階的に税負担を引き上げます。
令和3年度は、評価替えを起因とする税額の上昇を抑えるため、前年度と比較して価格が上昇する場合、令和2年度課税標準額に据え置かれます。納税者の負担は令和2年と同じですが、評価額そのものは改定されているので、しっかり確認しましょう。
◆宅地評価は相続税と異なります
宅地は地方税法の定める「固定資産評価基準」により評価されます。固定資産税の路線価が設定される地域では、路線価に画地補正率を乗じ、さらに修正率を乗じて1㎡あたりの土地評価額を算定します(修正率は毎年設定)。なお、画地補正率は、市町村(東京23区は東京都)の条例で独自に定めて適用することができます。
固定資産税路線価は、相続税の路線価と異なり、基準年度の前年1月1日(令和3基準年度は、令和2年1月1日)の地価公示価格、または不動産鑑定評価額の概ね70%で設定されます。また補正率は、相続税の補正率と同様のものが設定されていますが、地区の区分や適用される数値は相続税と異なるので注意が必要です。また令和3年度の修正率は、令和2年1月1日から令和2年7月1日までの地価の下落状況を反映して路線ごとに設定されています。今年は減額修正されている路線が多くあります。
◆所有土地の評価額をチェックする
令和3年度の評価額は、納税者の側でも固定資産税の路線価、画地補正率、修正率を使用して算出できます。市区町村の固定資産税課に出向けば、土地評価額を閲覧できるほか、担当者に問い合わせて評価額の根拠を教えてもらうこともできます。一度ご自身で土地の評価を確認してみてはいかがでしょうか。
7月12日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月12日までに納付)
7月15日
●所得税の予定納税額の減額申請
8月 2日
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日)